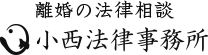養育費
養育費
子どもがいる場合の養育費の分担は、婚姻中は婚姻費用の分担、離婚後は養育費の分担の問題になります。
養育費とは、子の監議について必要な事項として、家庭裁判所が、非監護親から監護親に支払いを命じる子の養育費に必要な費用をいいます。
実務は、原則として、養育費支払い義務が発生する場合を20歳未満の子がいる場合としていますが、20歳未満でも仕事をして経済的に自立し、またはそれが期待できる者は除かれると考えられています。
他方、子が成年であっても、大学又は専門学校など高校卒業後も高等教育を受けている場合については、扶養義務者の資力、学歴などの家庭環境を考慮して、その環境で大学進学が通常と解される場合や、病気療養中の場合などは、養育費が認められることがあります。
養育費の算定方法
従来、家庭裁判所の実務においては、養育費の算定は、子が義務者と同居していると仮定すれば子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し.義務者が支払うべき額を定めていました。
具体的には、まず、権利者・義務者の総収入から、職業費、公組公課及び特別経費(医療費・住居費等)を差し引き、基礎収入を認定します。次に、義務者、権利者及び子それぞれの最低生活費を認定します。そして権利者・義務者の分担能力の有無を認定します。さらに、子が義務者と同居していると仮定し、義務者の基礎収入を義務者と子の各最低生活費等の割合により按分します。最後に、子の生活費を権利者・義務者双方の基礎収入の割合で按分し義務者の負担分を認定するという方法です。
現在の家庭裁判所及び高等裁判所等の実務においては、権利者・義務者の各収入、子の数、年齢に応じた養育費の算定表に従い、養育費の算定がなされています。
算定表の例外
算定表の幅を超える額の養育費の算定を要する場合は、算定表によることが著しく不公平になるような特別な事情がある場合に限られるとされています。
住宅ローン
住宅ローンの支払額は、算定表において特別経費として考慮されている標準的な住居に関する費用と比較して高額であることが多く、義務者がそこに居住していてもその負担が大きくなる場合もあります。また、義務者が自宅を出た後も、権利者の居住する自宅の住宅ローンを支払っている場合には、権利者は自らの住居に関する費用の負担を免れる一方、義務者は自らの住居に関する費用とともに権利者世帯の住居に関する費用を二重に支払っていることになります。
なお、 婚姻中に購入した不動産の住宅ローンは、本来、離婚に伴う財産分与において共同の債務であることを前提として清算されるべきものですから、養育費の算定に際しては、原則として考慮する必要はないということになります。しかし、不動産がオーバーローンの状態であるため、清算をすることなく、義務者がそのまま支払を継続している場合には、実質上の権利者の債務を、義務者が負担していることになります。そして、そのような場合には、義務者の負担を何らかの形で考慮すべきです。
その考慮方法としては、義務者の収入から住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法や算定表による算定結果から一定額を控除する方法などが考えられます。
私立学校の学費等
算定表は、子の生活指数を定めるに際し、公立中学校、公立高等学校の学校教育費を考慮するのみで、私立学校の学費その他の教育費は考慮していません。そこで、義務者が、子の私立学校への進学を承諾している場合など、その収入及び資産の状況等からみて義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合には、養育費の算定に際し、私立学校の学費等を考慮する必要があります。
義務者の収入が算定表の上限を超える場合
算定表が予定する基礎収入の割合は、算定表記載の収入を前提として算出された公租公課や特別経費の割合を前提としていますから、総収入がその記載の上限額を超える場合には本件算定表によることはできません。また、高額所得者の場合、生活実態も様々であるから、その面でも算定表の予定する基礎収入割合を用いることはできません。さらに高額所得者の生活実態を見ると、その収入をすべて生活費に充てることは少なく、貯蓄等に回されるとも考えられますので、基礎収入すべてを標準的な生活費指数に基づいて、按分比例して子の養育費を算定することには疑問があります。
このように、義務者の収入が算定表の上限を超える場合には、各事案の個別的事情を考慮して養育費が算定されるべきです。
養育費の決定
養育費についての取決めは口頭でも有効ですが、取決めの内容を明確にして、後日の紛争を避けるため、夫婦双方が署名押印した書面を残しておくとよいでしょう。
養育費の取決めについて、公証役場で「約束を守らない場合は強制執行をしても構いません。」という文言をつけた公正証書を作成しておけば、義務者からの支払いが滞った場合に、裁判をしなくても、公正証書を債務名義(強制執行力のある書面)として義務者の給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となりますので、養育費の支払確保に有効です。
離婚後の養育費について、当事者間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。調停が不成立になると、審判手続きで必要な審理がされたうえで、審判がされます。
過去の養育費
養育費は過去の分も含めて請求できますが、いつの時点からの養育費を請求できるのか、また、過去の養育費の全額について分担を請求できるのかについては問題があります。
請求の始期については、扶養(養育費)を請求した時点からとする審判例、扶養権利者の要扶養状態、扶養義務者の扶養可能状態(経済的余力)という事実があれば、具体的な扶養義務、扶養請求権が発生するとしたうえで、過去に遡って多額の負担を命じるのが公平に反する場合には、相当の範囲に限定するという審判例があります
事情の変更
離婚の際に養育費を取り決めた場合でも、離婚時に予測できなかった事情が生じたと認められる場合には、相手方に対し、養育費の増額や減額、支払期間の延長の請求をすることができます。
離婚時に予測し得なかった事情の変更とは、親や子の病気、怪我による長期入院、父母の勤務する会社の倒産による失業、物価の急激な上昇による養育費の増大などをいいます。
さらに、養育費の増額請求が認められるためには、事情の変更のあったことを前提に、請求の相手方において増額に応じられるだけの経済的な余力のあることが必要です。
養育費の増額請求において問題とされるものに子どもの教育費の増大があります。しかし、私立学校等に入学する際の入学金や四年制の大学、短大、専門学校等のいわゆる高等教育についての教育費が養育費に含まれるかについては、親の社会的地位、経済的余力、学歴、家庭環境等、子の学習意欲、などの事情を考慮して個別に決められているのが現状です。
養育費の減額請求についても、請求が認められるためには事情の変更が必要です。離婚調停時よりも父の収入が著しく減少したばかりでなく、再婚後の家庭の生活費を確保せねばならない等、生活状況が大きく変化したことが明らかであるとして、そのような事情変更を考慮し、調停で定められた父の養育費を減額変更した事例があります。
いったん調停・審判で決まった養育費の額が、その後の事情変更により、相当でなくなった場合は、改めて養育費請求の調停・審判を申し立てて変更することになります。
養育費を請求しないとの約束
義務者と権利者との間で、養育費を請求しないとの約束をした場合であったとしても、養育費の請求は可能です。養育費は子どものための生活費であり、親は子どもを扶養する義務があります。
養育費を請求しないという約束は、法律的には二つの側面を持ちます。
一つは、この約束を、親権に服する子の法定代理人として権利者が子の父に対する扶養請求権を放棄したものと捉える場合です。しかし、子どもは扶養権利者として、親に扶養を請求する権利があり、この子どもの扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません。したがって、子の法定代理人として子の父に対する扶養請求権を放棄する約束は無効と考えます。
他方、義務者に養育費を請求しないという約束を、父母間の養育費の分担について、義務者の負担をゼロとすることを合意したものと解すれば、合意は有効なものと見ることができます。しかし、審判では、その場合でもその効力は権利者と義務者夫との間の効力であり、子が扶養を必要とする状態にある場合、子ども自身が義務者に扶養料を請求するのを妨げるものではないとされていました。
その後、養育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討し、その内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至るときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく行使でき、また、合意後、事情の変更があり合意内容を維持することが実情に沿わず、公平に反するに至ったときは、扶養料の請求や増額の請求ができるとの審判例が出されました。
この審判の後は、①子の福祉を害する特段の事情があるかどうか、②合意後の事情の変更があるかどうかという見地から合意の効力を検討する判例が増えています。
養育費を一括で支払えるか
養育費は、養育費が子どものための生活費であることから、原則、毎月支払わなければなりません。
しかし、子どもを引き取って育てていく親の立場としては、養育費の一括払いは将来の支払いが確保されて大変心強く有り難いことです。調停離婚の場においても、監護者となる母親から養育費の一括払いの要求が出されることがあります。もちろん、相手方が合意することが大前提であり、実際に一括払いで解決するケースはごくわずかです。
理由は、金額が多額になること、一括払いにより子どもとの縁が切れてしまうような結果になることに対する不安、親権者、監護者となる母親に対する不信感等にあるようです。
養育費の一括払いを実現するためには、まず義務者に財産的基盤があることが前提ですが、一括払いされる養育費を子どものために使うことについての義務者の権利者に対する信頼感が必要となります。また、権利者も養育費さえもらえればそれでよいという態度ではなく、義務者と子供の面接交渉に協力するなど、いくつかの条件が満たされる必要があります。
調停で父母双方が養育費の一括払いに合意した場合でも、裁判官は一括払いとした場合の法律的な問題点を改めて説明し、合意が揺るぎないことを確認したうえで一括払いを認めているようです。
なお、一括払いの問題としては、母親が父親の信頼に反し自分自身のために消費してしまい、子が再び要扶養状態となってしまうおそれがある、子どもが途中で死亡してしまう可能性がある、支払われる養育費の額によっては贈与税の支払義務が生ずる可能性があるなどがあります。
履行の確保
協議離婚の際に公正証書を作成し、養育費の支払義務についても定めていた場合には、公正証書に基づき強制執行をすることができます。
一方、離婚について、口頭や公正証書以外の書面で養育費の取決めをしただけだった場合には、①地方裁判所に契約に基づく債務の履行請求として訴えを提起する、若しくは、②家庭裁判所に改めて養育費支払いの申立てをする方法により、まず、養育費の支払義務を確定する方法があります。
養育費の支払い確保の手段としては、①強制執行、②履行勧告、③履行命令、金銭の寄託、⑤審判前の保全処分等があります。
①の場合、強制執行力のある書面(債務名義)が必要です。②、③、④は家庭裁判所において、養育費についての判決がなされたか、調停調書、審判書に養育費の支払義務が記載されている場合に利用できる制度です。⑤は、家庭裁判所に養育費についての審判を申立てをしたときに急を要する事情がある場合に、審判に先だって仮差押え、仮処分等の保全処分を命じてもらうものです。
強制執行
強制執行は、判決や審判・調停調書など強制執行力のある書面(債務名義)により養育費が定められている場合に、債務名義に基づいて地方裁判所に強制執行の申立てをし、支払義務者の財産から強制的に支払いを確保する制度です。
履行勧告
履行勧告は、家庭裁判所の調停調書や審判調書、判決書に養育費の支払いが記載されている場合、義務者が支払いを履行しないときは家庭裁判所において履行状況を調査のうえ履行を勧告し、支払いを督促してくれる制度です。申立て手数料は不要です。調査に際して、家庭裁判所調査官は、支払義務者の事情についてもある程度理解を示しながら、当事者双方に対して必要なアドバイスや調整を行うことで、養育費支払い義務が自発的に履行されるよう促しています。
履行命令
履行命令は、履行勧告によっても養育費が支払われない場合に権利者から申立てがあると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期限を定めて義務の履行を命令する制度です。この命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられるという制裁があります。
金銭の寄託
金銭の寄託は、調停や審判において養育費等の支払義務を定めた場合、支払義務者の申出により、家庭裁判所が権利者のために養育費等の金銭の寄託を受けることができるという制度です。養育費等を直接受け渡すことが難しい場合などに、家庭裁判所が養育費等を代わりに受け取って権利者に交付する制度です。
審判前の保全処分
審判前の保全処分とは、家庭裁判所に子どもの監護費用分担の審判、扶養の審判などの申立てをしてまだ本案の審判が確定する前に、当事者からの申立てに基づき、強制執行を保全したり子の急迫の危険を防止する必要があると裁判所が認めたときに行われる仮差押え、仮処分、その他の必要な保全処分をいいます。この処分により子どもの授業料分に当たる扶養料の仮払いの仮処分を命じたり、養育費の仮払いの仮処分を命じた審判例があります。
権利者が再婚した場合の義務者の養育費支払い義務
権利者が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をした場合には、義務者の養育費支払い義務は当然になくなるわけではありませんが、子の扶養義務は第一次的には養父にあるため、義務者が養育費の減額を請求すれば、減額が認められる可能性が高くなります。
なお、子どもを連れて親が再婚しても再婚相手と連れ子との間には当然には親子関係は発生しません。再婚相手と連れ子が養子縁組をして初めて法律上の親子関係が発生します。
養子縁組により子は養親の嫡出子としての身分を取得しますので、養親が未成年の養子に対して扶養義務を負うのは当然ですが、それにより実親の扶養義務が当然になくなるわけではありません。
ただし、再婚により子は養親に扶養されることになりますので、子に対する関係では法律上は養親と実親は共に扶養義務者ではあっても、養親が一次的な扶養義務者、実親が二次的な扶養義務者になると解されています。
子が母の再婚相手と養子縁組をした後に、前夫に協議離婚の際に定めた養育費の支払いを求めたケースで、前夫は母や養父に劣後する扶養義務を負うにすぎないとして、前夫に対する養育費の請求を却下した審判例、父母が離婚し、父母双方が離婚後別の相手と再婚し、子が再婚相手と養子縁組したケースで、実父からの養育費減額請求に対して事情の変更を理由に請求を認めた審判例があります。
再婚相手が子と養子縁組をしない場合は、義務者が子に対して第一次的な扶養義務を負うことに変わりはありません。しかし、その場合でも、再婚相手が子の養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担するようになった場合には、養育費を取り決めた離婚時に予測し得なかった事情の変更があるとして養育費減額請求が認められる可能性があります。